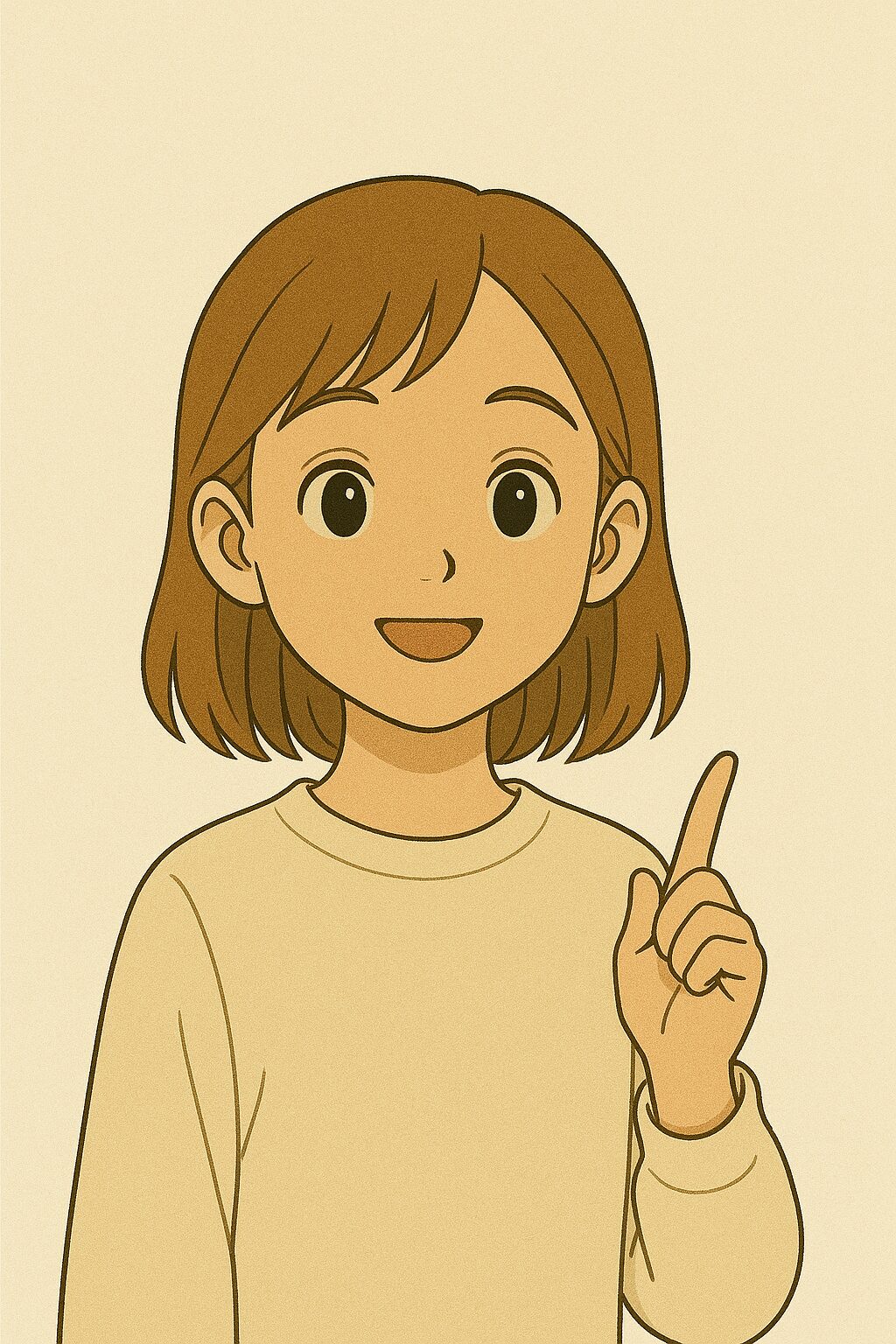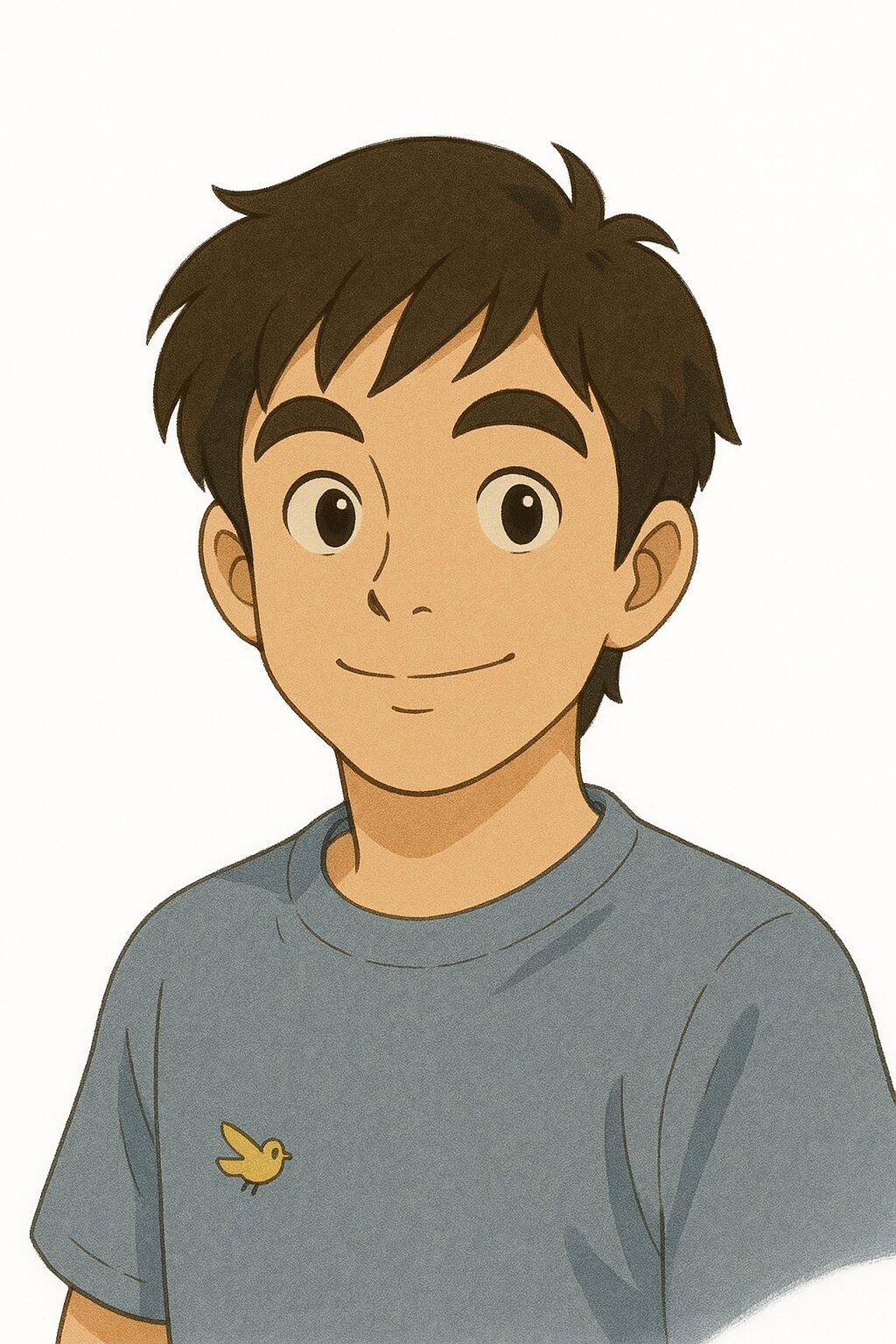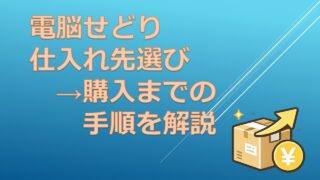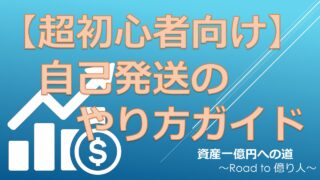ネコポスとクリックポストってどう違うんですか?
発送できるサイズや物は似てるけど、安心感や使い勝手が違います。トラブルリスクや発送スタイルに応じて使い分けるといいよ
この記事はこんな人に向けて書いています
- 発送トラブル(破損・未着)を経験した人
- せどり初心者で自己発送に慣れてきた人
- 自己発送ができずに困っている人
自己発送をするのにとても便利なクリックポストとネコポス
費用も送れるサイズもどちらもほぼ同じで、「どっちを使えばいいの?」と迷う人は多いと思います
ただ、よく見ると使い勝手や補償内容に大きな違いがあります
この記事では、実際に両方を使っている私の体験をもとに、それぞれの特徴や使い分け方について、解説していきます
- クリックポストとネコポスの違い
- 料金・サイズ・補償・スピードの比較
- 使い分けの基準
クリックポストは「安く・手軽・深夜でも発送できる」手軽派向き
ネコポスは「補償あり・翌日配達・安心重視」な人におすすめ
つまり──
- 一人暮らし、副業せどらーなど、時間を優先したい人はクリックポスト
- 家族がいて集荷を頼める環境なら、ネコポスで安心・確実に
どちらも優秀な発送手段なので、
生活スタイルに合わせて使い分けるのが、自己発送を続けるコツです
なお、ネコポスの補償は最大で3,000円/個です
販売金額が総額で3,000円を超える商品は
- 複数個に分けて発送する
- 補償が厚い発送方法に切り替える
などの、発送方法見直しも検討したほうがよいかもしれません
目次
Amazon自己発送でよく使われるクリックポスト・ネコポス比較
クリックポストは「安く・簡単・手軽」な発送方法
ネコポスは「安心・早い・補償あり」な発送方法
どちらもA4サイズ・厚さ3cm以内の商品を送れますが、補償とスピード、発送場所が大きく違います
| 比較項目 | クリックポスト | ネコポス(ヤマト運輸) |
|---|---|---|
| 料金 | 185円(全国一律) | 185円(沖縄除く) |
| サイズ | 縦34cm、横25cm、厚さ3cm以内・重さ1kg以内 | 縦31.2cm、横22.8cm、厚さ3cm以内・重さ1kg以内 |
| 追跡 | あり | あり |
| 補償 | なし | あり(上限3,000円※) |
| 発送場所 | ポスト投函 | コンビニ・営業所・集荷可 |
| 支払い方法 | ネット決済 | 各種キャッシュレス・現金可 |
| 配送スピード | 1〜3日 | 翌日配達(地域により当日) |
※ネコポスは補償がある一方で「補償上限3,000円」なので
複数商品をまとめて送る場合には総額に注意が必要です
🔗公式サイトはこちら
👉日本郵便(クリックポスト)公式サイト
👉ヤマト運輸(ネコポス)公式サイト
クリックポストの特徴と自己発送で使うメリット・デメリット
📦 安く・軽く・壊れにくい商品
- トミカ・雑誌・文房具・CD・薄型プラモデル
- 緩衝材で包んでも厚さ3cm以内に収まるもの
メリット
- ポスト投函だけで完結
- 深夜でも発送可能
- 発送用ラベルはHPから出力可能
デメリット
- 高額、壊れやすい商品には不向き
- 保証はなく、破損・未着の際には泣き寝入りするしかない
- 厚さオーバーの場合は発送してもらえない場合有り
3cmを超える商品をクリックポストで発送したことがあります
梱包したのは紙封筒。端は3cmに収まっていましたが、中心部分が膨らんで3cmを超えてしまっていました
これまで同じ商品を何度も発送していたので特に気にせずそのまま投函しました
ところが数日後、自宅のポストに、返送理由(サイズオーバー)と「郵便局に保管している」と記載された紙が投函されていました
郵便局で確認するとサイズオーバーで送れないとのこと
「今までは送れていたんですが・・・」と伝えても、認められませんでした
郵便局や担当者によって判断が変わるのかもしれませんが、返送されると出荷遅延となるリスクがあります
規定のサイズはしっかり守って発送しましょう
ネコポスの特徴と自己発送で使うメリット・デメリット
🐱 壊れやすい・価値のある小物・返品が怖い商品
- トレカ・高額フィギュアのパーツ・アクセサリー・電子部品
- 箱潰れで価値が落ちるコレクション系
メリット
- 補償あり(最大3,000円)
- 翌日配達でスピード安定
- 専用箱なしで自由梱包OK
デメリット
- 郵便ポストでは送れない
- 専用ラベルの発行が必要
- 受付の手間がある
Keiの体験談
ネコポスで発送した商品が購入者から「商品が届かない」と連絡があったことがありました
追跡番号を確認したところ、商品は「配達済」
購入者に「ご家族が受け取ってないか」を確認しましたが、一人暮らしとのこと
そこでヤマト運輸に確認を依頼し、購入者には謝罪の上、全額返金で対応しました
数日後、ヤマト運輸から「商品が見つからない」と連絡があり、商品代金と送料を補償をお願いしてみることにしました
ヤマト運輸から「商品代金が判る書類の提出をお願いします」とのことでしたので、販売金額が記載されたamazonの納品書を印刷して提出しました
商品代金なので仕入れ金額?とも思いましたが、あえて販売金額の記載されている納品書を出してみました
その後、示談書にサインして商品代金(1,800円)と送料(185円)の全額補償を受けました
あれこれ手続きするのであれば面倒だとも思いましたが、せどりをやっていく上でこれも経験と思い、補償を申し出ました
ところが、手続きは思っているより簡単でスムーズに対応してもらえたことに驚きました
この補償があるという安心感は、ネコポスを選ぶ一つの理由になっています
Keiの体験談②
ネコポス補償は“上限”がある話
1500円の商品が3個売れたので、まとめてネコポスで発送しました
サイズ的には問題なく送れたのですが
配送中の事故で商品が破損してしまい
購入者には全額返金で対応しました
その後ヤマトの補償を申請したところ
ネコポスの補償は1個あたり上限3,000円までとのことで
販売金額(4,500円)に対して差額が発生しました
損失は出ましたが、購入者に差額負担を求める形になると
大きなクレームにつながる可能性があります
最初から全額返金で対応してよかったと感じています
🔗ネコポスの補償上限に引っかかったときの購入者とのやり取りについては「【実録問合せ対応】破損クレーム対応の記録|購入者から感謝された理由」で紹介しています
Keiの体験談③
ネコポスを営業所に持ち込んだ時の話
普段、ネコポスは集荷をお願いしていましたが、その日はタイミングが合わずに営業所に直接持ち込みました
今まで受付でサイズを測られたことはなかったのですが、その日はきっちりスケールで測定がありました
「申し訳ありません。ネコポスサイズを超えているので受付ができません」
・・・ということで、その場は持ち帰ることとなりました
自己発送のラベルも印刷していたので、自宅に帰りいつものように集荷を依頼してみました。
集荷に来たスタッフさんはいつも通り測定せず、そのまま持って行ってもらえました
もちろん、ルール上は厚さ3cm以内が原則です
今回のように集荷と営業所では対応が違うことがあります
微妙な厚さの商品を営業所に持ち込む際には、専用スケールでしっかり確認をしておくと安心です
自己発送セラーが失敗しないための発送方法の選び方
自宅にいて、家族が集荷の対応をしてもらえるのであれば
「早い・安心・便利」なネコポス一択です
- 早い:翌日配達
- 安心:3,000円までの補償あり
- 便利:自宅まで取りに来てもらえる
ただし、ネコポスの補償は最大3,000円(1個あたり)なので
販売金額が高い商品や、複数商品をまとめて送る場合は注意が必要です
一方で、単身赴任中の今は集荷の対応ができません
便利な集荷がアダになってしまっています
そこで私は
- 平日の発送は自分でポスト投函できるクリックポスト
- 土日はネコポス
と状況に合わせて使い分けることで、無理なく自己発送を続けられています
また、単身者でも宅配BOXが設置できるのであれば
宅配BOXを使って集荷をしてもらえるので
平日でもネコポスを使える場面が増え、発送の幅が広がります
Keiの体験談
ネコポスとクリックポストを使い分けて自己発送をしていますが、ネコポスで送る商品を誤ってポストに投函してしまったことがありました
出社前に自己発送の商品が売れて、慌てて準備
平日なので本来ならクリックポストで発送する予定でしたが、なぜかネコポスのラベルを印刷して封筒に貼ってしまいました
クリックポストよりネコポスの方が作業の手順も少なく、慣れていたのもあり、焦りと重なってミスにつながったようです
自分ではクリックポストで発送するつもりだったので、そのまま出社途中でポストへ投函
集荷時間になって出荷通知をしようとクリックポストのサイトを確認しても、該当する件名が出てこない
不思議に思ってセラーセントラルを確認すると、すでに「出荷済み」
ハッと気づいて郵便局に電話して発送を止めてもらいました
実際は、クリックポストのラベルを貼っていないので発送されるはずもなかったんですが、念のため確認してもらい、商品を無事に回収
郵便局の方も非常に丁寧に対応してもらいました
会社帰りに郵便局で受け取り、ヤマト運輸の営業所に持ち込んで発送
なんとか出荷遅延を避けることができました
💡教訓:ポストに投函する前に、出荷ラベルはしっかり確認しましょう
🔗宅配BOXを使ったネコポス運用については
「【体験談】自己発送は在宅不要|宅配BOX+集荷でネコポス発送」
🔗宅配BOX集荷の注意点については
「【体験談】自己発送で宅配BOX集荷を依頼する時の注意点|「時間指定なし」の落とし穴」
🔗一人暮らし×副業せどらー向けの平日の自己発送手順はこちら
👉【一人暮らし×副業せどらーの自己発送】出社前30分の朝活術
👉【一人暮らし×副業せどらーの自己発送】昼5分の出荷通知
まとめ|自己発送の使い分けで作業効率と利益を両立しよう
クリックポストもネコポスも自己発送する人にとっては欠かせない発送手段です
どちらも送料が安く、うまく使いこなせば利益率を大きく高めることができます
その中でも集荷の対応が可能であれば、ネコポスが「早い・安心・便利」で非常に優秀です
一方でポストに投函するだけで済むクリックポストは、時間的な自由度が高く、私のような単身者にはとても便利です
それぞれの特徴を理解し、自分の生活スタイルに合わせて使い分けることで、どんな状況でも自己発送を続けることができます
特に、プライムデーから年末商戦にかけては、FBA納品の受領やFBAからの発送にメチャクチャ時間がかかる時期です
なかなか受領されずに販売機会を逃したり、商品到着の遅れで返品になることも珍しくありません
そんな時期でも、自己発送であれば在庫管理と販売スピードを自分でコントロールできます
無駄なストレスを減らし、チャンスを逃さないためにも、状況に応じた発送手段の使い分けが大切です
FAQ
Q.クリックポストとネコポスはどっちが早く届きますか?
A.ネコポスの方が早いです。地域によっては「当日〜翌日」に届くこともあります
クリックポストは1〜3日かかることが多いので、スピード重視ならネコポスがおすすめです
Q.壊れやすい商品はどっちで送るべきですか?
A.壊れやすい・高額な商品ならネコポスです
補償(3,000円まで)があるので安心感があります
クリックポストは補償がないため、破損や未着時は自己負担になります
Q.一人暮らしで集荷が難しいときはどうすればいいですか?
A.自宅での集荷が難しいならクリックポストが便利です
ポスト投函で完結するので、仕事前や夜でも発送できます
私も単身赴任中は、平日はクリックポスト・土日はネコポスで使い分けています
Q.ネコポスの補償上限(3,000円)を超える商品は送っても大丈夫?
A.送ること自体はできますが、万が一の事故では上限以上は補償されません
販売金額が3,000円を超える場合は
配送方法の見直しや複数口での発送なども検討したほうが良いかもしれません
【関連記事はこちら】
- Amazon自己発送の一時停止と再開方法
⇒ 【記事を確認】 - 初めてのAmazon自己発送手順ガイド
⇒ 【記事を確認】 - せどりの梱包資材13選|最初に揃える必須アイテムを徹底解説
⇒ 【記事を確認】 - Amazon自己発送のおすすめ設定と遅延ゼロ運用術
⇒ 【記事を確認】