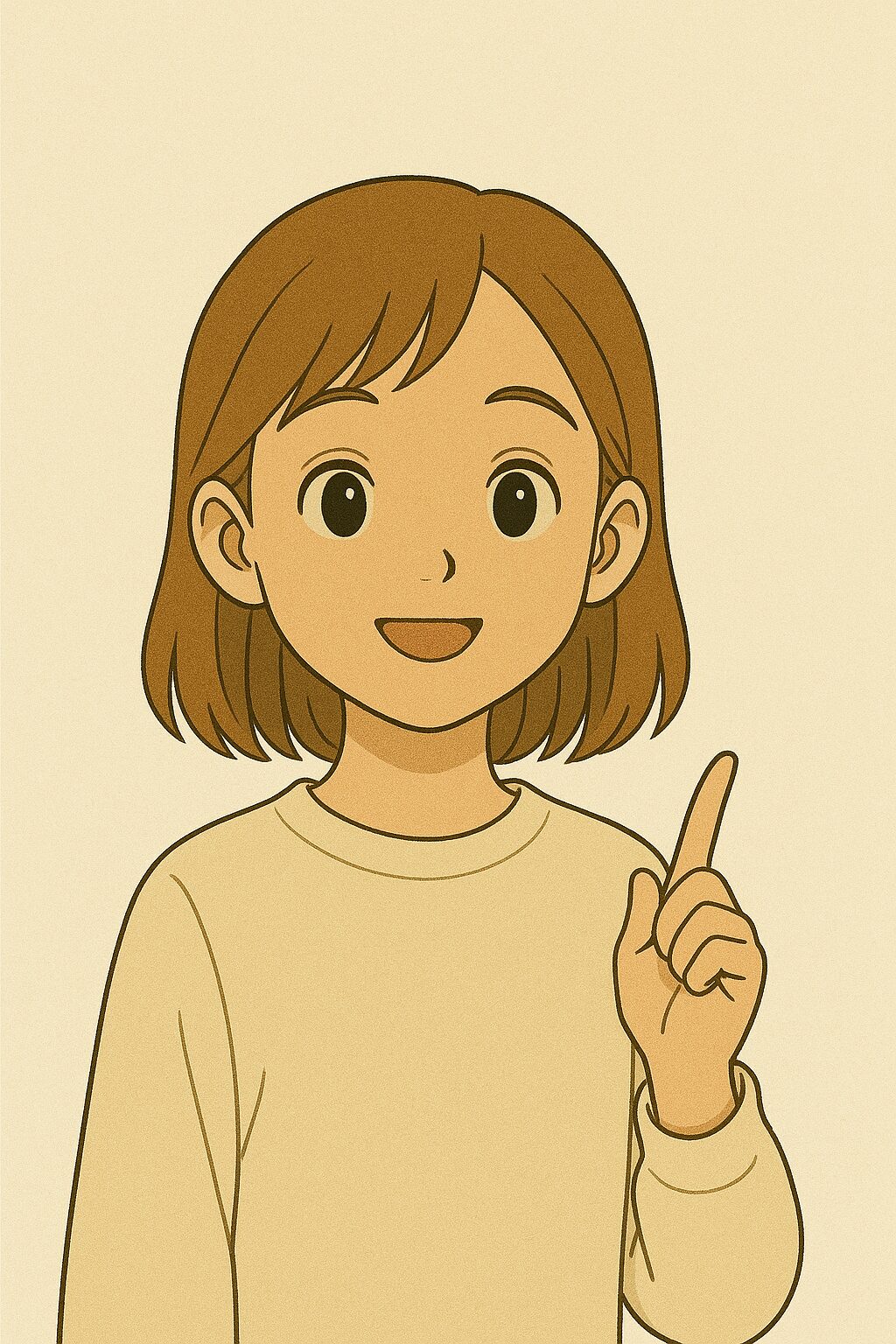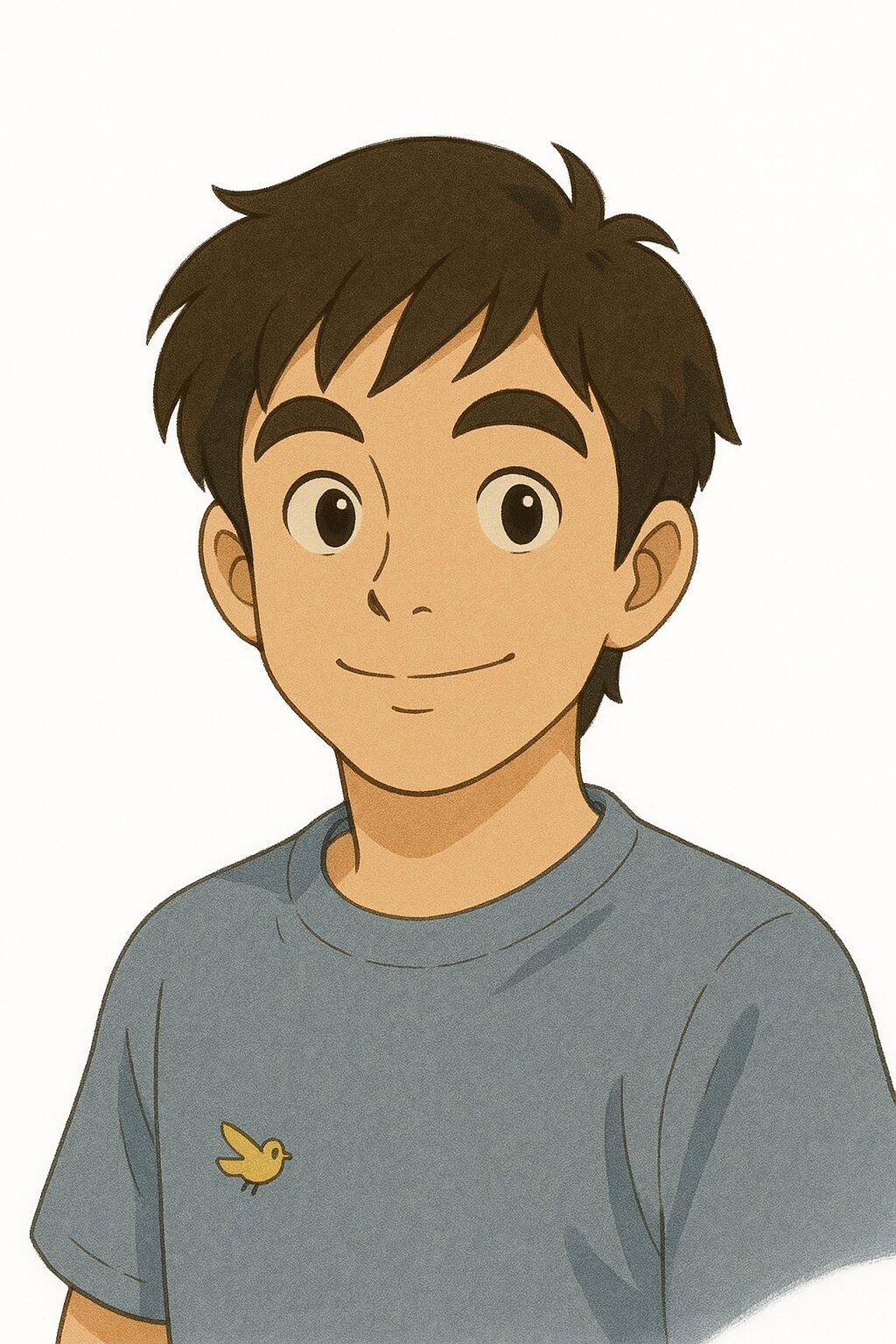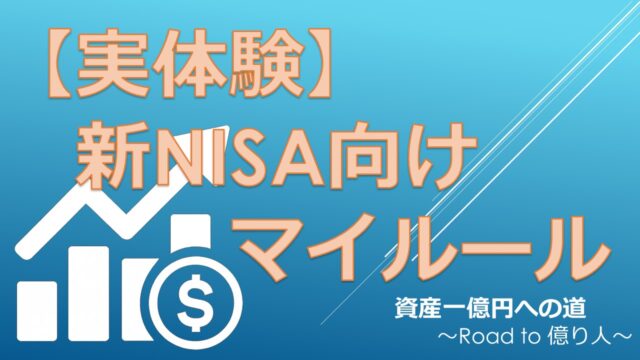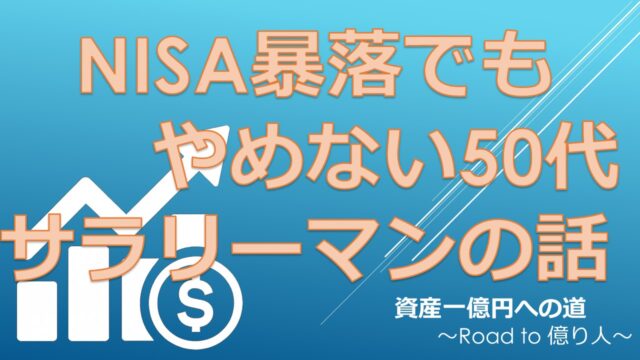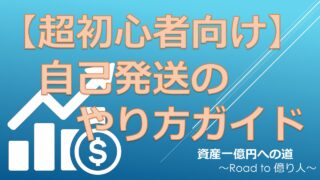投資って何にどれくらいお金を使ったらいいの?貯金を全部投資に回すのも、失敗したとき怖いし。
そうですよね。私も初めは、どこまで投資にお金を回していいかわかりませんでした。
この記事はこんな人に向けて書いています。
- 投資に興味はあるけれど、家族に反対されそうで一歩が踏み出せない方
- 50代からの資産形成で、リスクを抑えて「安心できる方法」を探している方
- お金だけでなく家族との関係も大切にしながら投資を続けたいと思っている方
投資を始めるとき、初めにぶつかる壁は「どれだけお金を投資に回せばいいのか?」という疑問です。
他にも、「何を買えばいいのか?」「いつから始めればいいのか?」など、わからないことが多すぎて、初めの一歩が踏み出せない人も多いのではないでしょうか。
私自身も40代後半に旧NISAを活用して投資を初めましたが、当時は知識ゼロ・経験ゼロの状態で、手探りで投資を始めました。
「何から始めればいいのかわからない」「損をしたらどうしよう」と不安を感じている投資初心者の方に向けて、私がどうやってその不安を乗り越え、投資を続けてこられたのか。
その過程を実体験ベースでお伝えしていきます。
- 50代から投資を始める際の不安を減らす考え方
- 安心してほったらかし投資を続けるための5つのルール
- 夫婦で資産を共有する方法とメリット
目次
投資を始める前に決めた5つのマイルール!それは妻との約束
投資を始めた当初は、私も不安を抱えていましたが、それ以上に不安を感じていたのは「妻」でした。
私たちは共働きで、本業収入もあるとはいえ、すでにアラフィフ。
これから先、老後の資金を確保していかなければなりません。
「普通に定年まで働けば、それなりに貯金できるのに、あえてリスクを取って投資をする必要があるのか?」
それが、妻の率直な疑問でした。
妻は、もともとリスクを取らない性格で「大切な貯金を投資に回す」=家計の危機に直結する不安があり、投資に後ろ向き。
不安を残したまま、二人の共有財産で投資を始めれば、いつか夫婦間で価値観のズレから夫婦仲もうまくいかなくなる。そんな危機感がありました。
そこで私は、ネットで情報を集めて、「投資のマイルール=妻との約束」を作ることにしました。ルールを明確にしたことで、妻も安心して納得してくれました。
結果として、このマイルールが私自身にとっても「安心して長期に投資を続けられる土台」になりました。
- 生活費の1年分は現金で確保しておく
- クレカ積立に限定して長期投資
- 投資に回す上限は生活費を除いた余剰資金のみ
- 投資先はインデックスファンドのみ
- 資産の推移は夫婦で共有する
この後、それぞれのルールについて具体的に説明していきます。
生活防衛資金の確保|1年分の生活費を現金でキープ
まず最初に決めたのは、「絶対に手をつけない生活防衛資金」を確保することでした。
当時の我が家の毎月の支出は、だいたい40万円ほど。
そして貯金は約1,000万円。そこから、生活費の12ヶ月分=約500万円を「何があっても触らない資金」として銀行口座に残すことにしました。
これだけの貯金があれば、たとえ会社が倒産したり、病気や事故で働けなくなっても、最低限の生活を1年間は維持できます。
「最悪の事態が起きても、生活が破綻することはない」この安心感があったからこそ、投資に踏み出すハードルが一気にさがりました。
クレカ積立で自動化|長期投資を無理なく継続
毎月の積立額は、カード積立の上限である33,333円(旧制度当時)からスタートしました。(旧NISAのつみたて投資枠は年間40万円が上限)
当時の我が家の毎月の収入は、だいたい60万。生活費に40万かかったとしても、残りで「家計を圧迫せずに無理なく積立ができる」という判断です。
利用したのは「SBI証券×三井住友カード」のクレカ積立。
毎月自動でクレカ積立が実行されるため、証券口座の残高を気にする必要もなく、一度設定すれば「ほったらかし」でOKというのが最大の魅力でした。さらに、積立額の1%分のVポイントももらえるため、お得感がありました。
そしてNISAで積み立てをする上での、もう一つのマイルール。それは「一度積み立てたものは、何があっても売らない!」というルール
短期的な価格変動に一喜一憂せずに、コツコツ積み立て、じっくり育てていく。このルールを決めたことで、相場の上下に振り回されずに投資を続ける心の安定が得られました。
「市場から退場していると、“稲妻が輝く瞬間”に居合わせることはできない」
(原文:You can’t afford to miss the market’s best days)
この有名な格言が示す通り、株式市場ではごくわずかな上昇日が、長期リターンの大半を占めると言われています。
だからこそ、「市場に居続けること」が最大の投資戦略。
そのためにも、“売らない”というマイルールは、自分にとって絶対守るルールの一つとなりました。
生活費を守る資金管理|余剰資金だけを投資に回す
クレカ積立のほかに、当時の貯金から500万円を特定口座で積立投資に回すことにしました。
ただし、リスク回避のため「一括でドンと投資」するのではなく、ドルコスト平均法を活用し、時間を分散させながら投資信託を購入しました。
具体的には以下のルールを決めて投資を進めました。
- 投資元本:500万円(特定口座)
- 分散期間:12ヶ月
- 毎月の投資額:30万円
- 購入日:毎月15日
⇒「クレカ積立」が毎月1日に実行されるため、日付をずらして時間の分散を意識 - 投資元本の残り140万円は「相場下落時の追加投資用」に待機資金として確保
⇒利益率▲5%になったら、待機資金の残金の半分を追加投資
このルールを決めた理由は、「無理なく」「焦らず」「相場にビビらず」投資を継続するためです。実際、投資を始めてから数ヶ月は含み損が続きましたが、あらかじめ追加投資用の資金とルールを決めておいたおかげで、焦ることなく冷静に対応することができました。その結果、後に訪れた相場の回復局面で、大きな利益を確保することができたのです。
やみくもに投資するのではなく、あらかじめ“自分ルール”を決めておくことで、相場の上下に振り回されず、淡々と投資を続けることができました。
インデックスファンドに投資|シンプルで分かりやすい投資先
投資先は、個別株やアクティブファンドではなく、リスクを抑えられるとされるインデックスファンド一本に絞ることにしました。
検討したのは、いわゆる王道の3本:
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
- eMAXIS Slim 全世界株式(いわゆる「オルカン」)
その中から、以下の理由で最終的に私は「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」を選びました。
- 米国は先進国の中でも数少ない人口増加国で、今後の成長にも期待が持てる
- 物価高や景気後退の懸念はあったものの、AIなどの先端分野で世界をリードしている
- 過去100年以上にわたり、短期的な価格変動もあるが、S&P500は長期的に見れば右肩上がりを続けてきた実績がある
- 投資初心者でも続けやすい、信託報酬の安さ(低コスト)も魅力のひとつ
個別株のように企業を選ぶ必要もなく、アクティブファンドのように中身を細かくチェックする必要もありません。
“何も考えずに、ただ積み立てる”だけで世界経済の成長の果実を得られる。これこそが、インデックス投資の最大のメリットです。
その中でも、米国企業500社に分散投資できるS&P500は、成長性と安定感のバランスが非常に高く、私にとって「ほったらかし投資に最適な投資先」になりました。
夫婦で資産を共有|定期的な情報交換で安心感も共有
どれだけ準備をしていても、投資には不安がつきもの。
妻と一緒にマイルールを作ってスタートした投資ですが、最初のうちはやはり不安が残っていたようでした。
特に投資を始めたばかりの頃は、「本当に大丈夫なの?」と、気が気でない様子。
そんな不安を少しでも和らげるために、毎週末、資産の推移や値動きを妻に共有するようにしました。(その頃は、日々の値動きを確認していたので「ほったらかし投資」とはいえませんでした・・・)
さらに、相場が下がったタイミングでの追加投資についても、妻に相談してから判断。
金額の大きさや家計への影響も含めて一緒に確認することで、安心感を持ってもらえたと思います。
私自身も、相場が下がった時は不安がありましたが、妻に話すことで安心できたこともあります。
相場下落時の対応についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、良かったら参考にしてみてください。
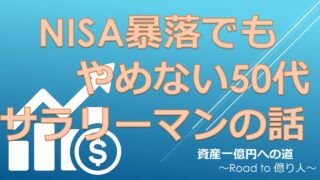
最初は「リスクのある投資はちょっと…」という反応だった妻も、資産の増減を一緒に見ていくうちに少しずつ投資に興味を持ち、新NISAスタートのタイミングで自分の口座を開設し、つみたてNISAを始めるようになりました。
まとめ|自分たちに合ったルールで投資を続けよう
投資には正解がありません。でも、自分なりの基準(ルール)をもっておくと、「相場が下がっても焦らず続けられる」ようになります。
- 生活防衛資金を守る
- 無理のない金額で積み立てる
- 理解できる商品だけに投資する
これだけでも、初心者にとっては大きな安心材料になるはずです。
投資は“自分だけのもの”ではなく、家族の未来にもつながるもの。
だからこそ、我が家では「マイルール=妻との約束」を作って、2人で安心できるカタチを探しながら続けています。
このマイルールは、旧NISA時代に私が実際に守っていたルールです。2024年から新NISAがスタートし、非課税枠や積立の仕組みも大きく変わりました。
当時と同じルールでの運用は難しいかもしれませんが、皆さんも自分自身でマイルールを決めて、安全に気楽な「ほったらかし投資」で、将来の「ちょうどいい自由」を手に入れましょう。
新NISAと旧NISAでは、非課税枠や制度の仕組みが大きく変わりました。
さらに、妻もつみたて投資を始めたことで、我が家の投資ルールにも変化が生まれています。
次回は、新NISAに合わせて見直した、私たち夫婦の「新・投資マイルール」をご紹介します。
「制度が変わったけど、どう対応すればいいの?」と感じている方のヒントになれば嬉しいです。
是非チェックしてみてください。

【関連記事はこちら】
この他にも、「投資」や「せどり」に関する初心者向けの解説記事をまとめてあります。
よろしければ、こちらから他の記事もチェックしてみてください。
この記事は、「ちょうどいい自由」を求めて資産形成中の普通の50代サラリーマン「Kei」が、自身の実体験をもとに執筆しています。
⇒運営者プロフィールはこちら